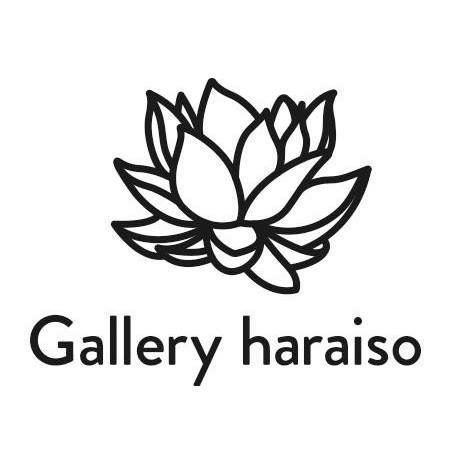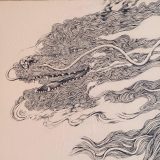時代の終わり
映画界に新しい潮流を起こしたヌーベルバーグの巨匠ジャン・リュック・ゴダールの訃報が世界中に広がった。
90年代後半、卒業制作で映像を選択したのがきっかけでゴダールの映画にたどり着き、そこで「格好良さ」について知ることになる。
昨夜、哲学者の千葉雅也が
「ゴダールは難解だった、と言われるが、基本的に、意味がわかりやすいものはカッコ悪い、意味がわからないものはカッコいい、のである。」
と呟いていた。
言い得て妙とはこのことで、本当に訳がわからないけどなんか「カッコいい」のがゴダールの映画だったように思う。
同じ頃よく見ていたフェデリコ・フェリーニも実に難解で気狂いレベルは2人とも群を抜いていたが、なぜか何度も見ることを止められない作品を作る監督であることに変わりはない。
91歳という長い人生の幕を自らの意思で合法的に閉じたことも興味深い。
この辺りは平野啓一郎の「本心」や映画PLAN75にも通じる。日本でそんな日が来るのかはわからないが、人生の幕の閉じ方についてはもっと語られて整備されるといい。
たまたまテクノ法要というイベントブースで30分ほど20代の女僧の方と「死」について語り合った。
葬儀のこと、墓のこと、埋葬のことなど実に明るく楽しく語るという初めての経験をした。
QOLが叫ばれる中、最後についてもっと建設的に語る場が生まれることを願う。
4ヶ月前に執り行われた兄の葬儀は家族葬で、実にアットホームな時間だった。義姉と甥っ子が兄のために一生懸命最後の儀式をより兄が喜ぶような形を考えていたことがわかる内容で、兄の好きだった曲がピアノの優しい旋律で流れていた。
その曲目から、ああ、この曲確かに兄が好きだったなと思い出した時、
「あれ?私の子どもたちは私の好きな曲とか知ってるのかな?」
と急に不安に駆られる。
実際尋ねると
「どうせママのことだからピアノのなんかあれでしょ」
と言われる。実に不安。
そこから脳内パニック。
どうしよう、好きでもなんでもない曲を選択して流されていたらとぐるぐる思考を巡らせたが、そうだその時はもう私の意識はそこにないのだと気づき一旦落ち着く。
でもやっぱり気になる。
兄の時はメジャーな曲だから葬儀場の人もすぐに弾くことが出来たが、自分の場合それが可能なのか…
ということで今日現在のリストを書いてみようと思う。
・はらいそ(細野晴臣)
・ありがとう(小坂忠)
・Walts for Debby(Bill Evans)
・平均律クラヴィーア曲集第1巻の第1番「プレリュードとフーガ」バッハ
・ピアノコンチェルト2あたり(ラフマニノフ)
はらいそは、ラストに「この次はモアベターよ」ってセリフが入ってるやつで。
ニュースレターを購読する